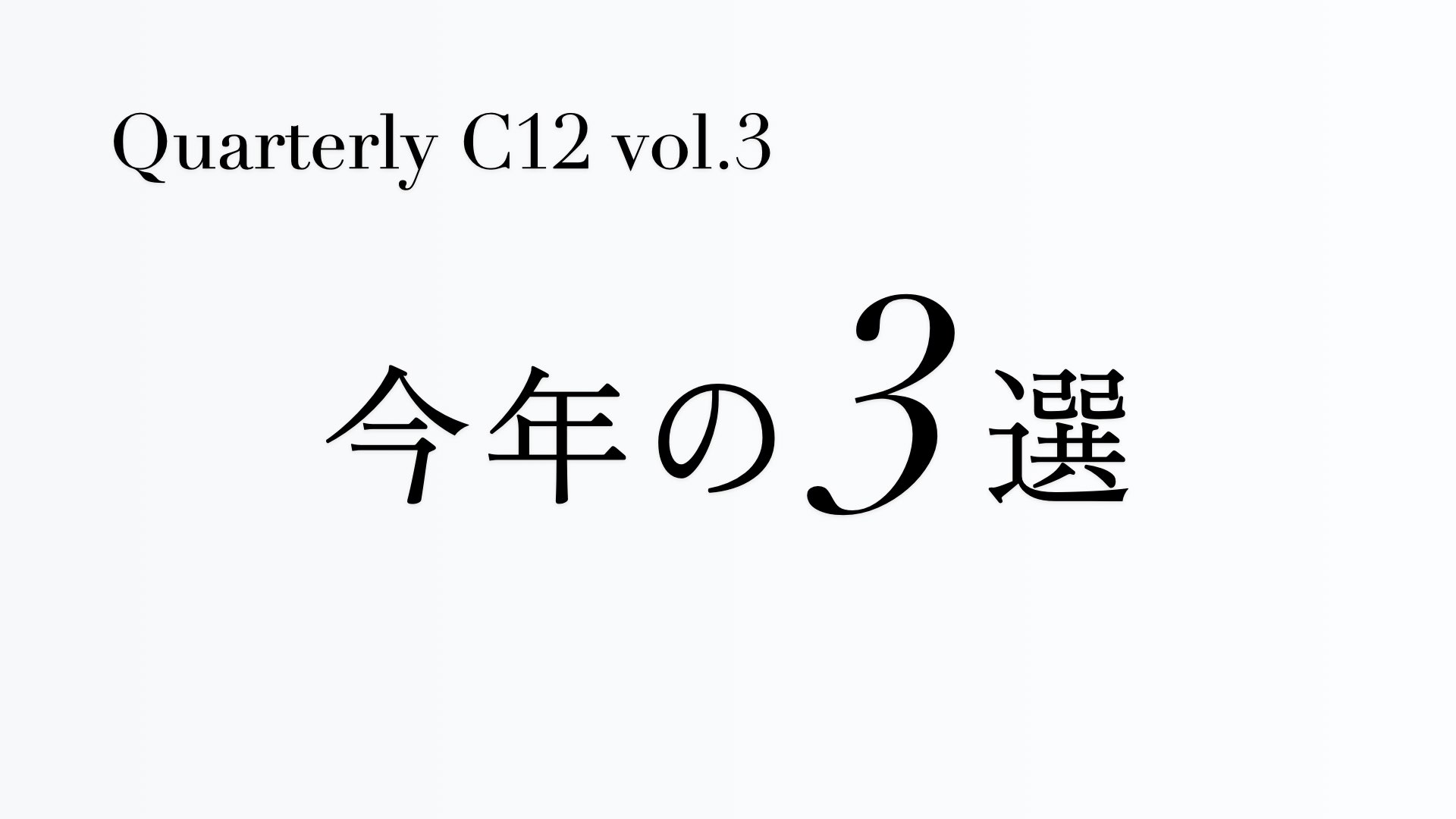辛い時間のながい1年ではあったけど、心に残ったものはある。
嬉しいことに頼んでくれる人がいるので、書き留めておこう。
寮で古本売りをしていたとき、隣で一緒に出店していた某先輩が勧めてくれた。読んだのはたしか今年の元旦で、この本は、年を重ねて本棚の中身が入れ替わっても、たとえ断捨離しても、手元に残したい一冊になった。
とにかく家に帰る。缶詰だの冷凍食品だのの買い置きはあるし、車のガスはまだだいぶ残っているはずだ。突然訪ねていって「なんか奢って」と言っても怒り出しはしない友人もいる。別に飢えるわけではない。
それは判っている。
何かをご馳走してくれるだろう友人相手に、「昨日ちょっと熱くなるまで打っちゃってさ、今日が日曜だってこと忘れててさ、ふと気が付いたらお金ゼンゼンなくってさ……」というような話を、ここでもまた露悪趣味を発揮してわざと笑い話のように話したところで、彼らは「しょうがないねえ」と呆れながら言うことはあっても(それくらいしか言いようがない)真剣に私を非難したりはしないだろう。
それも判っている。
なのにどうして、こんな気持ちになるのか。日曜の人混みを目にしたからか? その中にいるであろう「すこやか」や人たちを、心の中で罵倒したからか? それに対する自己嫌悪か? 自分があまりにも、もう今まで見たこともないくらい「しょうがない」からか?
判らない。判らないし、理由なんてどうだっていい。とにかくひとつ言えるのは、どういう理由にしろ、まったくずいぶんと恵まれた悩みをお持ちじゃないですか、いい気なもんすね、と、他でもなく自分自身が自分に向かって言ってやりたいような気がする、と言うことだけだ。鷺沢萠『私の話』(河出文庫:2005)pp.72-73
『私の話』を譲ってくださった先輩とは別に、鷺沢萠がとても好きな先輩が居て、その方がLINEで勧めてくれたのが2023年の夏ごろ。以来ずっと積ん読していて、この冬に読んだ。
刺さる内容だった。
自分のなかにある「善良さ」を見つめさせられ、自戒を迫られる読書体験だった。
ここで言う「善良さ」は、決して褒められた性格を意味しない。「善良さ」は、言いかえれば「世間知らずさ」であり、「意識的な振る舞い」=自己演出をしないまま、「ありのままの自分」をさらけ出していることへの、批判的な言辞である。欠如した「意識的な振る舞い」の代わりにあるのは、言いつけを守る従順さであり、演出無しに世に向かう無垢さである。だから、その人は、文字通り「善良」な存在でもある。
善良さはだから、「子供の世界」では、「無垢さ」「純粋さ」と言われて許されるけれど、「大人の世界」では、端的に「甘さ」であり、「ありのままで許される」などと思って、何の努力もしない「傲慢さ」と結びついている。演出の不在は、「大人たち」を苛立たせる。「善良さ」とは、周りの演技に助けられていることに気づかない、「鈍感さ」でもあるから。
福岡で学習塾を運営されている鳥羽和久さんが、こう書いている。
現代の若い世代にとって、ある程度の「演技性」を持つことがデフォルトの振る舞いとされています。そのため、自信がなかったり頼りないと見える人が、自身の「演技性」を駆使している様子を目にすると、そこに現実味や切実さを感じ取り、共感しやすくなる傾向があります。一方で、誠実さや素直さを前面に出しつつ、演技的な要素を欠いた人に対しては、「理想論ばかりで周囲との調和を欠いている」と感じられ、苛立ちを覚える場合があるようです。(2024.11.18) (強調は原文)
鳥羽和久さんのnote
この小説は、傲慢=架と、善良=真実という対位から始まり、しかし架が「善良な真実」を追ってみると、「真実の善良さの裏面に傲慢」が露わになり、真実自身は一度その自己認識を深くして傷つきながらも、架の「鈍感さ」(=善良さ)に救われていたことに気付いて終わる。
この小説が示唆するように、善良な人間がいるというよりは、誰しもが「善良さ」をさまざまな形で持っている。というか、誰もが自分や他人の中に「善良さ」を見出しながら過ごしている。そして相手が持つ「善良さ」=「鈍感さ」に救われることもある。
しかし、ともかく、都合が悪くなると「子ども」のコードに戻って、「善良さ」を「良きもの」として温存し、傷つくことを回避するのは、卑怯なことであると自分に言い聞かせたい。「善良さ」「鈍感さ」を自らの美徳と思って生きてはいけない。しっかりと大人として振る舞って、どうしても鈍感さが見えてしまう、くらいでいい。
演技性を生きるといえば、濱口竜介『偶然と想像』について、宮台真司と荘子itが評していたところがあって、これもとっても良かった。
噂に聞いてずっと見たかったけど、ソフト化されていておらず見られなかったドキュメンタリー映画。名寄の酪農家を訪ねたときに、上映会が催されていて、機会に恵まれた。
いやあ、なんどでも見たいなあ。