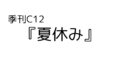古文に出てくる川といえば鴨川である、と高校の頃使っていた参考書に書かれていたのを覚えている。ご当地ネタを堂々と教科書に載せるなよ、といつもツッコんでいたのだが、京都に越してきて古の文人たちの気持ちが少し分かったような気がしている。鴨川は、他のどんな川よりも人との距離が近い。単なる川ではなく、人々が生きていく場所なのだ。鴨川の河川敷に腰かけていると、軽快なギターの音色と朗々とした歌声が、どこからともなく聴こえてくる。それらは川に集う人々や生き物、川の流れる音と共に、一つの音楽を奏で始める。
音楽。それは私にとってこの夏休みを象徴するものになった。友人や先輩との何気ない会話から、所属する軽音楽サークルの合宿や、熊野寮で開催された京都学生狂奏祭に至るまで、あらゆる場面で音楽に触れ、音楽とともに過ごした夏休みだった。聴く楽しさは勿論、パフォーマーや裏方として音楽を直接創り上げる楽しさを、深く知ることができた夏だったと思う。
私はやはり音楽が好きだ。音楽それ自体が確かな鼓動をはらんでいて、まるで一つの生き物のように聴き手に語りかけてくる。その言葉にもっと向き合ってみたいし、自分自身が語り手として、メロディーとリズムでしか届けられない生命を産み出してみたい。音楽で食っていくことほど険しい道はないし、将来それができるほどの才能に恵まれているわけでもない。それはよく分かっている。けれども音楽の熱にしばらく浮かされてみたい、許される限りこの時間に酔いしれていたい。イベントの締めにお決まりのように流れてくる、Oasisの”Don’t Look Back in Anger”を半ば叫ぶように歌いながら、そう思った。
音楽とは川のようなものではないか、と近頃よく思う。ひっそりとした所から湧き上がる静かな流れが、次第に力強くなっていく。人々や生き物が少しずつ集い始め、やがて流れと共に生きていくようになる。小さな子供の笑う声。恋人たちが囁くように話す声。ポタポタとこぼれ落ちる誰かの涙。川は、すべてを乗せてゆく。抑えきれない叫び。ほとばしる血の熱さ。押し殺されたわななき。音楽は、すべてを運んでゆく。そうして川は、音楽は、一日も休むことなく流れてゆく。
きっと誰しもが心の中に、自らの音楽を秘めているはずだ。それは年を経るごとに大きな流れとなり、人々を集め、他の誰かの音楽と交じり合って新たな流れを生み出す。
私の中にある川は、これからどんな流れになっていくのだろう。どんな人が集い、どんな川が私の一部となっていくのだろう。川で魚を探していた鷺が、河川敷の私をじっと見つめてから、夏の太陽の方へ飛び去っていった。