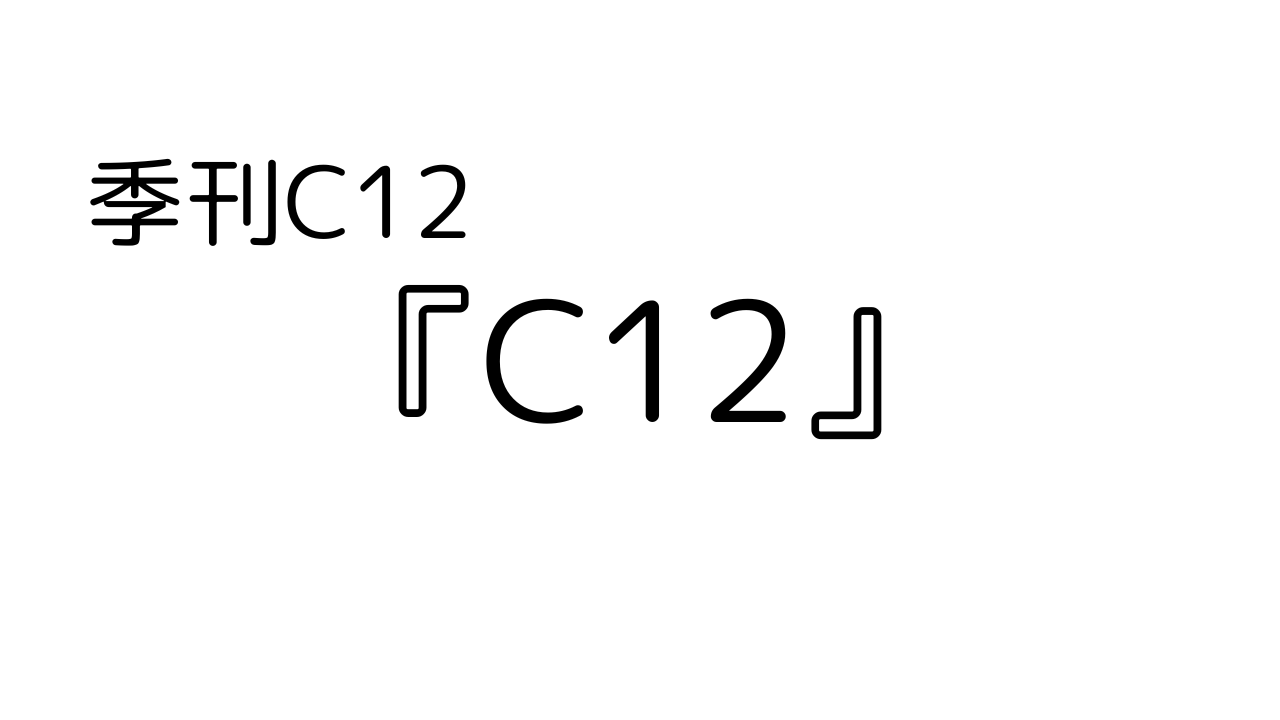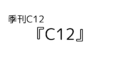京都の街へやってきて早くも三か月が経った。僥倖に恵まれて、私は高校を卒業してすぐに地元を離れた。別れを惜しむ故郷の人々が寄せてくれた期待を誇りに変えて、私は意気揚々と、この千年の都へ来た。しかし、自堕落な性分を改められるほど私は芯のある人間ではなかった。気付けば書き記すのも憚られるほど情けない生活を送っていた。
自分の人間性の馬鹿馬鹿しさを目の当たりにすると、愛する人々の喪失が私にのしかかってきた。私は甘えているだけだった。彼らはいつも、何者でもない自分の頭をそっと撫で、抱きしめてくれたから。彼らのそばにいるだけで、何者かになれる気がしていたから。そして私は、この期に及んでなお、今ここにはない彼らの温もりに縋りつこうとしていた。運命を恨みたいわけでも、これまでの事の成り行きを憎みたいわけでもない。けれども、現実を変える力もなく、ただ幾重にも幾重にもIFを積み重ねてばかりの自分は確かに存在している。お前は何者なんだ?何のためにここで生きているんだ?答えようもないくせに、何度も言葉で自分を殴ってしまう。
今回の季刊のテーマ、「C12」について思いを巡らす時、思い出さずにいられないのは、入寮当日のC12談話室だ。必死に抱えてきた荷物の整理と、同部屋の上回生への挨拶を済ませた私は、春の高揚感で胸をいっぱいにしながら、談話室へと足を運んだ。部屋の中には新入寮生と上回生とが十人ほど、炬燵の周りに座っていた。その輪の中に混じり、とりとめもない会話を交わす。あの日、私は特段の理由も資格もなく、「ただそこにいるだけ」だった。周囲の人々の名前は全然覚えていなかったし、彼らの人柄など知るはずもなかった。けれどもあの日の談話室は、あたたかさに包まれていた。「ただそこにいるだけ」の私を、静かに抱擁してくれていた。許してくれていた。その感覚は、それからもずっと変わっていない。C12は、何者でもない自分を受け入れ、何者かにしてくれる場所だと感じている。
この先数年続いていく、大学生活というモラトリアム。自分はここにいて良いのだろうか。ここに来て良かったのだろうか。気を抜くとハウリングするその問いを耳にしながら、私は今日も生きている。惰性で流れていく日々の中で、時々談話室に立ち寄ってみる。駄弁ったり、麻雀をしたり、炊事場で作った料理を食べたり。「建設的」と言えるのかよく分からないことをしながら、確かに思うのだ。私は、C12で生きている。